5回の転職と3度の後悔から見えてきた、後悔しない職場選びのヒント
「転職を繰り返すなんて、よほど問題がある人なのかもしれない。」
アラフィフにもなると、そんなふうに思われるのではないかと、不安になることがあります。
私自身、これまでに5回の転職を経験してきました。
決して、気軽な気持ちで職場を変えてきたわけではありません。
どの転職にも、それなりに理由があり、期待もあって決断したものです。
でもそのうち3回は「失敗だったかもしれない」と感じた転職でした。
とはいえ、その失敗も無駄ではありませんでした。
なぜなら、数々の違和感や後悔を経て、
ようやく自分なりの「職場選びの軸」が見えてきたからです。
それは、
- 安心して働けるか?
- 無理なく続けられるか?
- 自分の価値観と合っているか?
という3つの視点。
もちろん、すべての希望を満たす完璧な職場なんて存在しないかもしれません。
でも、この3つの視点を意識するようになってから、
「納得して働ける場所」に出会える可能性は確実に高まりました。
この記事では、これまでの転職経験と、実際に働いてみた現場で感じたことをもとに、
後悔しない職場選びのヒントをお伝えします。
40代・50代の薬剤師として、これからの働き方に悩んでいる方の参考になればうれしいです。
1. なぜ、転職で後悔したのか?
転職するときは、誰だって「今よりいい職場に行きたい」と思って決断しているはずです。私もそうでした。
でも、実際に働いてみると、「これは違ったな…」「正直しんどい」と感じる職場もありました。
特に強く後悔を感じたのは、在宅中心の薬局(A社)、内科クリニック門前の薬局(C社)、小規模病院(D社)での勤務です。どれも、当初は希望を持って入職したのに、働く中で「自分には合わない」「これでは続けられない」と思う出来事がありました。
1-1. 在宅中心の薬局(A社)|やりがい搾取と100時間残業の現実
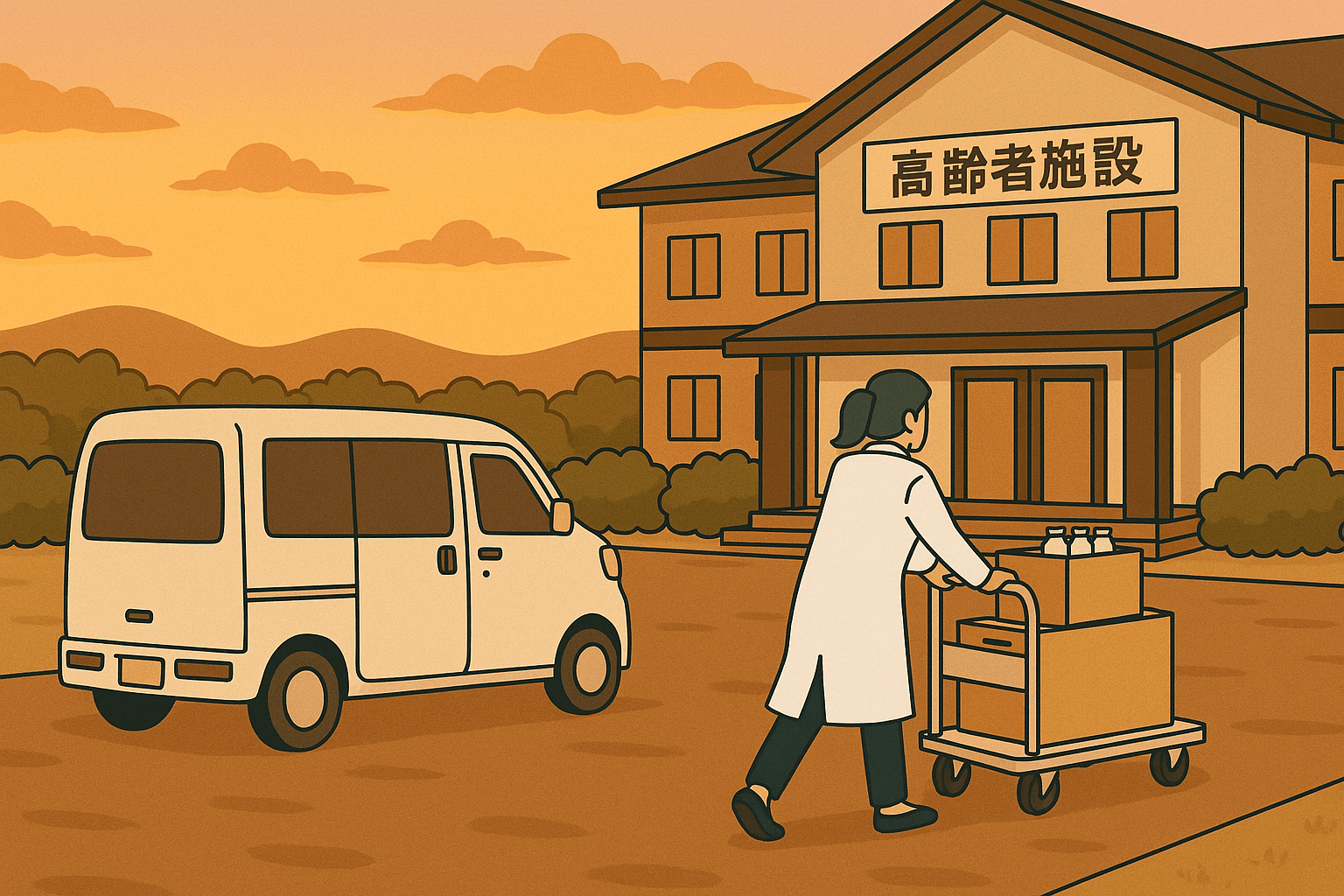
A社は、在宅業務に力を入れている小規模チェーン薬局でした。人手不足が常態化し、人事異動も多く6年働いて管理薬剤師を4店舗で経験しました。
当時は「新しい分野を学べる」と前向きに入社を決め、社長が業界紙などで取り上げられるほど注目されていたことも後押しになりました。
しかし現場に入ってみると、顔の見えない施設入居者の調剤・監査・配達が大量に発生し、臨時処方や施設看護師からの細かな指示に振り回される毎日。往診同行はゼロ、服薬フォローもままならず、ただただ業務に追われる日々でした。
月100時間を超える残業(10年以上前の話です)が常態化し、スタッフの入れ替わりも激しく、休日には無償の勉強会に「自主参加」が求められる。
「成長できる」と信じて入ったのに、いつしかやりがい搾取の職場になっていました。
1-2. 内科クリニック門前の薬局(C社)|調剤の怖さに気づいた

40代でC社に入社した時は、給与・勤務時間ともに申し分ない条件でした。自分自身、過去最高の年収、残業もほとんどなし。
…でも、現場に立った初日から違和感がありました。
監査は形だけで終わってしまい、スピード優先の調剤が常態化していました。
在庫管理も十分とは言えず、棚卸しは年1回の形式的なチェックのみ。薬の扱いに対する意識が低く、扱いがルーズな場面も見受けられました。
「これは危ない」「もし事故が起きたら…」という不安が募り、毎日がプレッシャーとの闘いに。
安心して働ける環境とは、とても言えませんでした。
1-3. 小規模病院(D社)|モラハラと隠蔽体質

病院勤務にもチャレンジしてみたい。そう思って入職したのがD社でした。注射薬や多職種連携に興味があり、スキルアップできるのではと期待していました。
でも、現実はまったく違っていました。
薬局長のハラスメントが横行し、特定のスタッフへのパワハラ発言が常態化。私自身も精神的に追い込まれることがありました。
さらに、調剤ミスがあっても処方医にとりなしてもらい、すぐに「なかったこと」にされる風土。患者さんの命に関わる場所で、これは絶対に許されないと思いました。
残業は月40時間以上あり、心身ともに限界に近づき、短期間で退職を決断しました。
1-4. 番外編(E社)|数字目標に追われる現場
M&Aにより転籍先となった大手チェーン薬局(E社)では、かかりつけ件数や在宅件数、イベント参加人数、OTC販促など営業的な数値目標が本部より次々に降りてくる日々。
数字を追うのがモチベーションになる人もいるかもしれません。
でも私は、患者さんに向けた営業がとても苦手でした。
そのため、プレッシャーばかりを感じて、どんどん疲れてしまったのです。
2. 納得して働けた職場もある
後悔ばかりの転職ではありません。
一方で、「ここに来てよかった」と思えた職場も確かに存在しました。
特に印象に残っているのが、安全対策を徹底していたB社と、無理のない働き方を実現できている現在の職場(G社)です。
2-1. B社|安全対策がしっかりした薬局での安堵

B社は中規模チェーン薬局で、マニュアルが整備されており、「安全を守る仕組み」が明確にありました。
たとえば、
- 調剤ミスを防ぐための電子監査システムが全店舗に導入されていた
- 過誤は当日中に本部や社長まで報告され、社内全体で再発防止策が共有されていた
- 薬歴も早くから電子化されており、業務の効率化や確認作業の明確化に役立っていた
といったように、薬剤師が安心して「本来の仕事」に集中できる環境が整っていたのです。
もちろん、業務量は少なくはありませんでしたが、「何かあっても職場が守ってくれる」という安心感は、精神的な安定につながりました。
詳しい内容はこちらの記事をご覧ください。
2-2. G社|無理なく続けられる環境で再び働く喜びを実感
現在勤務しているG社は、地域密着型の小規模薬局です。
正直、給与は過去の最高額には及びません。でも、残業はほとんどなく、有給も取りやすい。シフトも柔軟に調整できるため、生活とのバランスがとりやすく、心身ともに無理なく続けられる環境です。
日々の業務は地味かもしれません。でも、目の前の患者さんとの関係をじっくり築けるこの職場に、今は満足しています。
また、今後責任者となる若いスタッフと、対等な関係で意見を交わせる職場風土も心地よく、「支える側として関わりたい」と思える職場です。
3. 転職で学んだ、後悔しないための3つの視点
5回の転職を経て、ようやく私が「これだけは譲れない」と思えるようになったのが、次の3つの視点です。
3-1. 安心して働けるか
どれだけ給与が高くても、どれだけ条件が良くても、「安心して働けるか」は私にとって最重要の軸でした。
たとえばB社では、調剤過誤を防ぐ体制がきちんと整っていて、職場全体が“安全を守る意識”で動いていました。
「ルールがルールとして機能しているか」は、見学や面接の時点でもある程度感じ取れるものです。
一方で、以前の職場では、
「調剤監査が形だけ」「服薬指導の時間がない」「ヒヤリ・ハットを隠す文化がある」など、
薬剤師としての倫理観と現場の運用とのズレに、強い不安を感じることもありました。
“自分や同僚のミスが命取りになりかねない”——そう感じながら働くのは、とても消耗します。
だから私は、仕組みと風土の両面で“安全”を担保できる職場かどうかを、何よりも重視するようになりました。
3-2. 無理なく続けられるか
「定年まで働けるかどうか」は分からないけれど、「半年後・1年後も今のペースで働ける?」と問われて、
「YES」と思えるかどうか。
これが、続けられる職場かどうかの判断基準だと気づきました。
現在のG社では、勤務時間・休日・人員体制のバランスが取れていて、何より自分の時間を削りすぎなくて済むんです。
繁忙期もありますが、無理な残業を強いられることはなく、仲間同士でフォローし合える余裕があります。
昔の私は、「仕事だから、しんどくても頑張るのが当たり前」と思っていました。
でも、頑張りすぎて体も心もボロボロになってからでは遅いんですよね。
“長く働きたい”と思うなら、「続けられるか」の視点は甘く見てはいけない。
これも、後悔して初めて気づいた大切なポイントでした。
3-3. 自分の価値観と合うか
人によって「働きやすさ」の定義は違います。
バリバリ働いて出世したい人もいれば、家庭との両立を優先したい人もいる。
私にとっての「働きやすさ」は、現場に小さな提案が通ることや、患者さんと丁寧に向き合えることでした。
G社では、今後責任者になる若手スタッフと「こうしたらいいよね」と対話しながら業務改善に取り組んでいます。
そうした価値観の共鳴がある職場では、「やらされている」のではなく、「自分から動こう」と思えるようになります。
これまで私は、評価制度ばかりに目が向いていた時期もありましたが、
最終的に自分が納得して働けるかどうかは、その職場の“文化”と自分の価値観が合うかどうかだと痛感しています。
4. 3つの視点を、どう見極める?
「安心」「無理なく」「価値観の合致」
この3つを見極めるのは簡単ではありませんが、転職前の段階で意識できるチェックポイントはいくつかあります。
4-1. 安心して働けるか → ルールが“機能”しているか
見学や面接の場では、「調剤過誤を防ぐための仕組み」や「インシデント共有の体制」について、具体的に聞いてみることが大切です。
たとえば、こんな質問が有効です:
- 「処方箋の受付から調剤、監査、投薬までの一連の流れにルールや手順は決まっていますか?」
- 「調剤過誤やインシデントが発生した場合、社内でどのように共有され、防止策はどうされていますか?」
返答が曖昧だったり、“ルールはあるけれど形だけ”という雰囲気があれば、注意が必要です。
また、見学時の調剤室が雑然としてあちこちが汚れていたり、薬歴の運用が紙ベースで煩雑そうだったりする場合も、職場全体の安全意識や業務管理体制のゆるさが見えてくることがあります。
4-2. 無理なく続けられるか → シフト・残業・人員体制を確認
見学や面接で、以下のような点に注目してみましょう:
- 「月の残業時間は平均どのくらいですか?」
- 「シフト作成の流れや有給休暇の取得実績はどうですか?」
- 「他店舗への応援はありますか?」
また、「常に人手がギリギリ」「体調不良時のフォロー体制がない」といった話が出てきたら、長く続けるには不安な職場かもしれません。
4-3. 自分の価値観と合うか → 働く人たちと“感覚が近い”か
価値観のすり合わせは、正直なところ、数十分の面接や短時間の見学だけで完璧に見抜けるものではありません。
でも、いくつかの視点から「違和感がないか」「働く人たちとの距離感は近そうか」を、なんとなく感じ取ることはできます。
たとえば:
- 面接や見学時に、現場の雰囲気やスタッフの様子を少しでも垣間見られるか?
- 働き方や業務の説明に、現場目線の工夫や想いがにじんでいるか?
- 「うちは昔からこうだから」といった、頭ごなしの説明が多くないか?
ちょっとした雑談の空気感や、会話の中に出てくる言葉の選び方からも、その職場の“柔らかさ”や“合いそうかどうか”は伝わってくるものです。
それでも判断が難しいときには、こういう質問もおすすめです:
「現場スタッフの意見が実際に業務や運営に反映されたことってありますか?」
実際に意見が採用された事例があるかどうかを尋ねることで、現場の声が大切にされているかどうか、あるいは風通しの良さを感じられるかを見極めるヒントになります。
結局のところ、働く環境の快適さは、制度やシステムだけでなく、「誰と働くか」に大きく左右されます。
ほんの数分の雑談や、ちょっとしたやりとりからでも、「あ、この人たちとならやっていけそう」と思える職場に出会えることもあります。
“空気感が合うかどうか”は、数値で測れないけれど、大事な軸です。ぜひ、直感も大切にしてみてください。
5. まとめ|100点の職場はない。でも…
私はこれまでに何度も転職し、後悔も、納得もしてきました。
その経験から言えるのは、すべての条件がそろった“理想の職場”なんて、実際には存在しないということです。
でも——
- 安心して働ける
- 無理なく続けられる
- 自分の価値観と合う
この3つの軸のうち、少なくとも2つが満たされていれば、「この職場にしてよかった」と思える可能性が高いのではと、私は感じています。
転職は、運もタイミングも関係するもの。
でも、自分にとって何が大事かを理解していれば、たとえ失敗したとしても、次はその視点を活かすことができます。
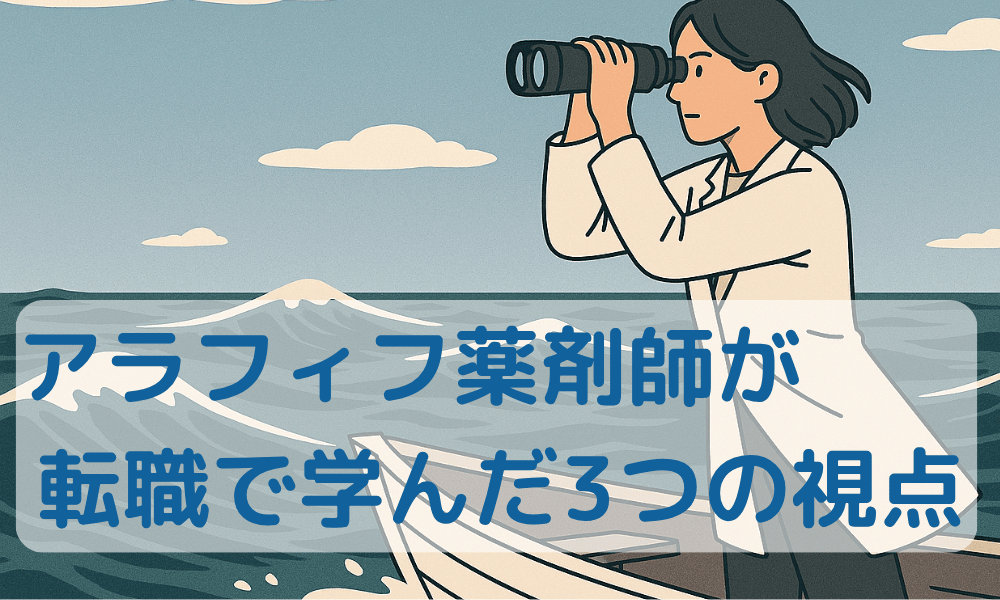
コメント