エージェントを使うと決めたあとに迷いやすいのが、 「どこを選べばいいの?」 「どう付き合えば後悔しない?」ということです。
実は、「どこが一番いいか?」という明確な正解はありません。
なぜなら、 担当者との相性や自分の目的によって合う・合わないが変わってくるからです。
この記事では、私が実際に体験してきた
「うまくいったこと」やちょっと失敗したな」と思ったことを交えながら
”付き合い方”にフォーカスしてお伝えします。
※「どのエージェントを選べばいいの?」という比較や評価については、別の記事でまとめる予定です。
担当者との相性は、想像以上に大事
どんなに大手のエージェントでも、結局は「誰が担当になるか」で印象がガラッと変わります。
たとえば、私が登録した2社のうち、ある担当者は連絡が遅くて「大丈夫かな…?」と不安になり、 結局そのエージェントの利用はやめてしまいました。
逆に、対応が丁寧でテンポよく連絡をくれる担当者とは、安心してやり取りができました。
「この人、話しやすいな」と思えるかどうか。 これは案外、大事な判断軸になります。
担当変更やエージェントの乗り換えもOK
「なんだか合わないな…」と感じたときに、無理して付き合い続ける必要はありません。
いきなり担当者本人に伝えるのが気が引けるときは、会社に相談して別の担当に変えてもらうのもよくある対応です。
また、1社にこだわらず複数のエージェントを併用して比較するのも、視野を広げるうえで効果的です。
複数エージェントの併用には注意点も
実際に複数のエージェントを使ってみると、
- 情報の幅が広がる
- 自分の市場価値を多面的に把握できる
といったメリットがありました。
ただ、面接が一社決まると「他も急いで受けましょう」と言われ、 面接ラッシュになることもあります。
内定が出たら一週間以内の返答を求められることもあり、 複数社のスケジュール調整はなかなか大変でした。
併用は有効ですが、無理のない範囲で活用するのが安心です。
信頼できる担当者とは、長くつながれる
私が最近利用したエージェントの担当者は、数年前に初めて相談した方でした。
当時はまだ転職を迷っていたのですが、 「今は現職を続けるのがいいかもしれませんね」 と無理にすすめてこなかったのが印象的で、信頼につながりました。
それ以来、「次に動くときはこの方にお願いしよう」と思い、 実際に再度お願いしました。
エージェントは転職のプロ、でも現場のことは自分でも確認を
エージェントは薬剤師業界に詳しくても、 実際に薬局で働いた経験がある方はほとんどいません。
たとえば「雰囲気がいいですよ」と言われても、 その根拠が「忙しいときでも目を見てあいさつしてくれるから」だったりします。
レセコン・薬歴ソフトの種類や処方せん枚数、在宅の有無などはすぐに確認できますが、 スタッフ構成や喫煙者の有無、休憩室の雰囲気など、細かいことはあいまいなこともあります。
現場情報で「気になること」は、しつこいくらい聞いてOK
私は以前、面接にうかがった薬局の休憩室がタバコ臭くて驚いたことがありました。
求人票にも喫煙の記載はなく、エージェントにも伝わっていなかったようです。
それ以来、「気になることは何度でも聞く」ことを心がけています。
遠慮せず、気になる点は細かく確認してOKです。
エージェントは「人と人との信頼関係」で動いている
担当者の多くは若手で熱意のある方が多く、 無料で何度も相談にのってくれるなど、サポートはとても手厚いです。
でも、連絡を無視したり態度が強めだったりする求職者に対して、 優先度が下がってしまうこともあると聞きました。
だからこそ、私たち求職者側も「最低限の礼儀」だけは意識しておきたいなと思っています。
連絡をやめるときも、「今回は見送ります」ときちんと伝えるだけで、印象は全然ちがいます。
また、エージェントは企業に対して求職者の印象を伝える場面もあるため、 よい関係を築けるにこしたことはありません。
40〜50代だからこそ、「年齢的な余裕」や「配慮」を持った関わり方ができたら素敵ですよね。
まとめ:主導権を自分に戻せば、エージェントは頼れる味方になる
エージェントとの付き合いで後悔しないために大切なのは、 自分が主導権を持つこと。
「どこで働きたいか」「どう働きたいか」を自分の言葉で整理して伝えることで、 サポートの質もグッとよくなります。
焦らなくても大丈夫。 納得して選ぶために、自分の軸をしっかり持っていきましょう。
今回の体験談が、少しでも参考になればうれしいです。
※「どのエージェントがいいの?」という点についても、 別の記事で整理できたらと考えています。
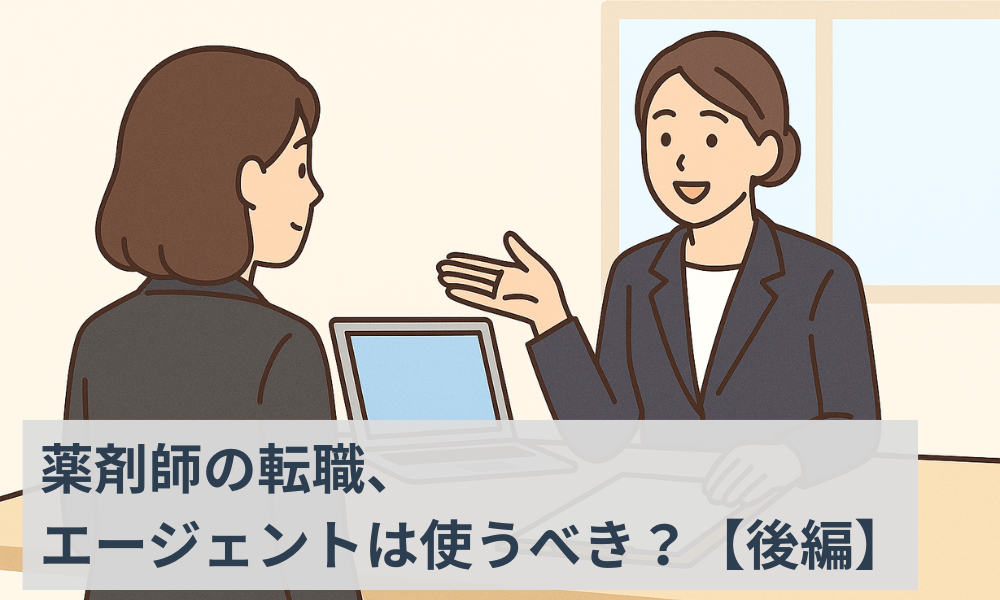
コメント